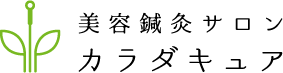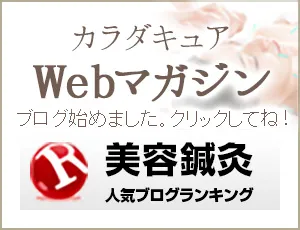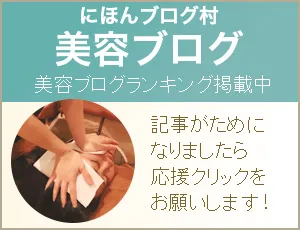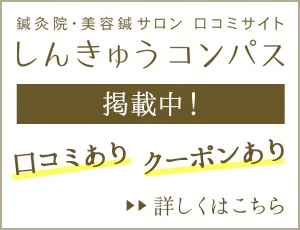こんにちは。
みなさん、鍼灸治療で使われる「鍼」には色々な種類があることはご存知でしょうか?
カラダキュアに通われている、または鍼治療の経験がある方には分かる方もいらっしゃるかもしれません。
今日はそんな
「鍼」についてどんなものがあるのか、みなさんに知っていただく為にまとめてみました。

◇鍼治療の定義とは?
まず鍼治療とは、接触または穿刺刺入することで身体に一定の機械的刺激を与え、それによって起こる身体の反応を利用し、病気の予防や治療に応用する施術です。
つまり刺さない鍼も、鍼治療に含まれているという事です。
最近は「刺さない鍼」という言葉も色々な所で聞くようになり、みなさんの間でも馴染んできたものかと思います。
これら刺さない鍼も実は古代の中国からあるもので、昔は石や竹を鍼にして使っていたと推察されています。
そのような鍼のカタチも気になりますが、まずはどのような素材があるのかそちらを見ていきましょう。
◇鍼の素材とは?
現在日本で主に使われている鍼の材料は、ステンレス、金、銀があります。
それぞれに特徴があり、使い分けられています。
ここでは和鍼と呼ばれる日本製のものについて主にまとめています。

- ステンレス
現在、1番鍼灸院で使用されているもっともスタンダードな素材がステンレスの鍼です。
耐久性に優れており、刺入しやすく折れにくい素材です。
高圧滅菌や通電にも耐えられるため、治療の幅も広く使えます。
更に、金や銀に比べ安価で、ディスポーザブルが主流の時代に合っていると思われます。
鍉鍼のステンレスタイプは、硬さや重さが適度なため初心者も使いやすくコントロールしやすいようです。 - 金
ステンレス鍼が主流になる前は、金鍼、銀鍼が主流でした。
ただ上記にも書きましたが衛生面と耐久性を考慮し、使い捨てしやすいステンレス鍼へと変わっていきました。
やはり滅菌消毒しているとはいえ、使い回しというワードはネガティヴに感じる方が多いのかもしれません。
もちろん、金鍼を使用している鍼灸院では徹底した衛生管理が行われていると思いますし、MY鍼と言って自分専用の鍼を購入してもらい保管している所もあるようです。
そのような金鍼ですが、なんといっても人体組織へのなじみが良いことが1番の良さだと思います。
耐久性には劣りますが、柔軟で弾力性に富んでいる為、刺入時の抵抗や痛みも少ないです。
敏感で痛みを感じやすい方なんかには、とくに良いかもしれませんね。 - 銀
金鍼とステンレスの中間のような鍼です。
柔軟で弾力性があり人体組織へのなじみが良く金鍼に比べ安価ですが、酸化しやすく腐食しやすいことが難点です。
銀鍼くらいの値段であれば、使い捨てでも使用している鍼灸院はあると思います。
腐食にだけ気をつけてれば、良いとこ取りの素材と言えますね。 - その他上記の3種類以外にも、銅、チタン、水晶、プラチナなどさまざまな材料が使用されることがあります。
特に刺さないタイプの鍉鍼(ていしん)には種類が多く、治療に応じて使い分けされます。
このように今と昔では少し主流の素材が変わっていたり、鍼の種類によっては使われる素材の種類も変わってきます。
では次に鍼の種類について見ていきましょう。
◇鍼の種類とは?
今、現在使われている鍼は約2000年前の中国で治療に使われていた「古代九鍼」の中から出たとされています。
さらにそこから進化し、特殊鍼として何種類か加わりました。
まずは、大元の古代九鍼からみていきます。
古代九鍼
- 破る鍼種類は、ざん鍼、鋒鍼(ほうしん)、鈹鍼(ひしん)の三種類です。
これらは皮膚を破る、所謂切開をする時に使われていたものです。
カタチはそれぞれ異なりますが、見比べるとざん鍼が1番現代のメスに近いことが分かります。
江戸時代ごろまでは、鍼師は今のように身体に鍼を刺すことよりも化膿した膿などを切開し除去することの方が多かったようです。
今は日本でも西洋医学が発達し、このような分野は医師のものとなり、東洋医学も日本独自の進化を遂げました。 - 刺入する鍼種類は、員利鍼(えんりしん)、毫鍼(ごうしん)、長鍼(ちょうしん)、大鍼(だいしん)の四種類です。
これは、みなさんも私たちも1番よく知るタイプの鍼ですね。
カタチはどれも今の鍼に近いです。
毫鍼は、漢字を見ても分かるように髪の毛のように細いという意味があるそうで、こちらが今使われている鍼の起源とされています。
その他の3つはどれも太く、長く、縫い針やキリのような見た目で、とても刺激に弱い日本では定着しずらかったのかなと思いました。 - 刺入しない鍼種類は、円鍼(えんしん)、鍉鍼(ていしん)の二種類です。
これらは皮膚を按ずる、擦るように使い、経絡や経穴を刺激し効果を与えるタイプの鍼です。
これらは上記の2つとは違い、あまり臨床での記録が残されていないようで、日本では実践的に使われておらず昭和以降に発展したと考えられます。

これらが中国から伝えられた古代九鍼と、その中でも現代まで残っている鍼の種類です。
鍼師の分野でなくなったけど、その先駆けで使われていたもの、時代に合わせて使われなくなったもの、今でも残っているものがあり面白いですよね。
- その他上記以外では、皮内鍼(ひないしん)、円皮鍼(えんぴしん)、小児鍼(接触鍼)、などがあります。
皮内鍼や円皮鍼は置き鍼と呼ばれるもので、短い鍼を長時間皮下にテープで固定しておくものです。
中国では、きん針と呼ばれ耳鍼療法に応用されます。
これら置き鍼はカラダキュアでも使われていますし、置き鍼が鍼ではなく、銀粒や皮下に入らない突起のタイプだと販売されているのを見たことある方もいるのではないでしょうか。
小児鍼では、身体に鍼を刺入することなく皮膚刺激によって治療を行います。
鍉鍼と少し似ていますね。
特に近畿地方で盛んに行われていた治療の1つで、生後2週間から小学生までが主な対象となります。
小児鍼に使われる鍼もまた種類が分かれ、集毛鍼(しゅうもうしん)、振子鍼、いちょう鍼、ローラー鍼、ウサギ鍼に分類されます。適応としては、疳の虫(小児神経症)、夜泣き、不機嫌、奇声、夜驚、食欲不振、風邪、扁桃炎、気管支喘息、仮性近視、眼精疲労、下痢、便秘、消化不良の治療に使われます。
◇鍼先(鍼尖)のカタチ色々
さて、今まで鍼の種類について書いてきましたが、鍼の先端、鍼尖にもカタチが色々あります。
鍼尖のカタチは刺鍼の方法や、流派によって異なっていてそれぞれに特徴があります。
- スリオロシ形…鍼尖より徐々に太くなる長い二等辺三角形のような形。
刺入しやすいが曲がりやすく、痛みを与えやすい。 - ノゲ形…鍼尖の上部約1.5㎜から細くしたもの。
刺入しやすく曲がりにくいが、痛みを与えやすい。・卵形…鍼尖が卵のように丸い形。
曲がりにくいが刺入しづらく、刺入時に鈍痛感を与えやすい。 - 松葉形…鍼尖のすこし上から細くなり、
ノゲ形と卵形の中間の形。
刺入しやすく、痛みも与えづらい。
このような種類があり、最後の松葉形が今、日本でより多く使われているカタチです。
そしてこの松葉形をさらにコーティング加工し、より痛みの少ないものの開発なども進められています。
古代から今までの知識と経験や、私たちの生活や身体の発達に合わせてこれからもより良いものが作られていくでしょう。
◇まとめ
みなさん、鍼の種類について覚えて頂けたでしょうか?
約2000年前から伝わっている古代九鍼、そのうちの毫鍼というものが現代で1番使われているという事は覚えていただけると嬉しいです。
鍼尖についてはさらっと書いたので、またどこかでお話したいと思います!
実際、どんな鍼を使ってるか見たい!という方はお気軽にスタッフまでお声かけください♩
当院は「真の美しさは健康から」をモットーに施術しています。
鍼灸の詳しい説明はこちらからどうぞ。